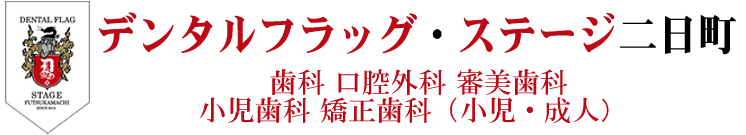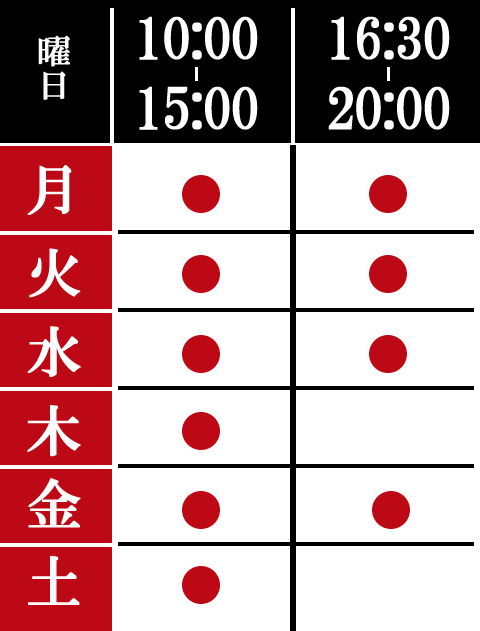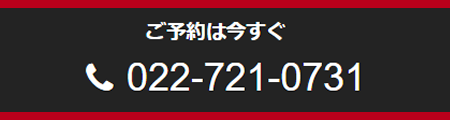こんにちは。仙台市青葉区の歯科クリニック『デンタルフラッグ・ステージ二日町』院長 前澤訓(マエザワサトシ)です。
みなさんは「歯周病の治療」というと、どんなイメージをお持ちでしょうか?
「歯石を取る」「よく磨く」「お薬を塗る」などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
実際、初期~中等度の歯周病であれば、歯のクリーニング(スケーリング)やルートプレーニングといった“非外科的治療”で改善することがほとんどです。
しかし、症状が進行し、歯ぐきの奥深くまで感染が広がってしまった場合には、それだけでは十分ではないこともあります。
今回は、「歯周病が進行したときに行われる外科的処置(手術)」について、わかりやすくお話ししていきます。
なぜ外科処置が必要になるの?
歯周病は「歯を支える骨(歯槽骨)」が溶けてしまう病気です。
初期段階では歯ぐきの腫れや出血だけですが、進行すると歯の根のまわりに深い歯周ポケットができ、歯石や細菌がどんどん奥に入り込んでいきます。
そのような状態になると、通常の器具では奥まで届かず、汚れを取りきれません。
このような場合、歯ぐきを開いて、直接目で見ながら汚れや感染組織を取り除く外科処置が必要になるのです。
外科処置を行うことで、
- 歯周ポケットを浅くする
- 歯の根をきれいにして、再感染を防ぐ
- 骨や歯ぐきの再生を促す
といった効果が期待できます。
外科処置の種類
歯周病の外科的治療には、いくつかの方法があります。
症状の程度や、歯の位置、患者さんの体調などによって使い分けられます。
① フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)
最も一般的な歯周外科処置です。
歯ぐきを部分的に切開して開き、歯の根や骨の状態を直接確認しながら、歯石や炎症を起こしている組織を丁寧に除去します。
処置後は歯ぐきを元の位置に戻して縫合します。
見えないところまでしっかりきれいにできるため、歯周ポケットが深い部分の改善に非常に有効です。
手術と聞くと不安になるかもしれませんが、局所麻酔で行い、痛みはほとんどありません。
術後は数日~1週間程度で落ち着くことが多いです。
② 骨の形を整える処置(歯周形成外科)
歯周病が進むと、歯を支える骨が不規則に溶けてしまい、歯ぐきの形もデコボコになってしまいます。
そのままにすると汚れがたまりやすく、再発しやすくなってしまいます。
このようなときに行うのが、歯槽骨整形術や歯肉整形術といった外科処置です。
感染した部分を取り除き、骨や歯ぐきの形を整えることで、清掃しやすい口内環境をつくります。
「見た目の改善」にもつながることがあるのが、この治療のメリットです。
③ 再生療法(GTR法・エムドゲインなど)
最近では、失われた骨や歯ぐきを再生させる治療も行われています。
これを「歯周組織再生療法」といいます。
代表的なものには次のような方法があります。
GTR法(組織再生誘導法)
特殊な膜を歯根のまわりに入れ、歯ぐきの細胞が骨の再生を邪魔しないようにします。
その間に骨が自然に再生していくのを助けます。エムドゲイン法
歯の根に「エムドゲインゲル」というタンパク質を塗り、骨や歯ぐきの再生を促します。
人体に近い成分なので安全性が高く、近年多くの歯科医院で採用されています。
再生療法はすべてのケースに適用できるわけではありませんが、骨の形や感染の範囲が限られている部分的な歯周病では、非常に効果的です。
④ 歯肉移植・根面被覆術
歯周病の進行や加齢などで歯ぐきが下がり、歯の根が露出してしまった場合に行う処置です。
主に、上あごの内側から少量の歯肉を採取して移植します。
これにより、
- 見た目の改善(歯が長く見えない)
- 知覚過敏の軽減
- 汚れの付着を防ぐ
などの効果があります。
「歯ぐきを取り戻す」ための外科的アプローチといえるでしょう。
外科処置の流れ
検査・診断
歯周ポケットの深さ、レントゲンによる骨の状態をチェック。
外科処置が必要かどうかを慎重に判断します。非外科治療(スケーリング・SRP)を先に行う
いきなり外科手術をするのではなく、まずは歯石を除去して炎症を抑えることが大切です。
これでも改善しない部位に外科処置を検討します。外科手術の実施
局所麻酔をして、歯ぐきを開いて感染部分を除去します。
処置時間は1本の歯に対して30〜60分程度が目安です。縫合・経過観察
歯ぐきを縫い合わせ、1週間前後で抜糸します。
その後は経過を確認しながら、メンテナンスへ移行します。
外科処置後の注意点
- 当日は無理に強くうがいをしない
- 激しい運動や長時間の入浴は控える
- 食事はやわらかいものを中心に
- 指や舌で触らないようにする
- 指定された薬をきちんと服用する
また、手術後はブラッシングの再開タイミングを歯科医師に確認し、無理せず進めることが大切です。
清潔を保ちつつ、治りを妨げないようにしましょう。
外科処置を受けたあとのメンテナンスが最重要!
外科治療は「最終手段」と思われがちですが、それで終わりではありません。
歯周病は慢性的な病気のため、再発防止のためには定期的なメンテナンスが欠かせません。
せっかく外科処置で汚れを除去しても、日々のケアが不十分だと、また細菌がたまり再発してしまうのです。
歯科医院での定期的なチェックや、フロス・歯間ブラシを使った毎日のケアを継続することが、長期的な安定につながります。
まとめ
歯周病の外科処置は、重症化した歯ぐきや骨を回復させるための大切なステップです。
「手術」と聞くと少し怖く感じるかもしれませんが、麻酔で痛みを抑え、安全に行うことができます。
・歯周ポケットが深く、歯石が取りきれない
・歯ぐきの形が複雑で、汚れがたまりやすい
・骨が部分的に失われている
といったケースでは、外科的アプローチが必要になることがあります。
そして、治療後こそが本番です。
ご自宅での丁寧なブラッシング、食生活の見直し、定期的な歯科メンテナンス――。
その積み重ねが、健康な歯ぐきを長く保つ秘訣です。
お口の中の違和感や出血が続くときは、早めに歯科医院へご相談くださいね。
進行していても、きちんと向き合えば回復のチャンスはあります。
デンタルフラッグ・ステージ二日町 院長 前澤訓(マエザワサトシ)

宮城県仙台市出身
日本歯科大学生命歯学部(東京)口腔外科第二講座大学院卒業
2010年 デンタルフラッグ・ステージ二日町開業 院長
宮城県歯科医師会代議委員
宮城県歯科医師連盟評議委員
宮城県日本歯科大学校友会理事
社会福祉法人未来福祉会理事
仙台市立広瀬中学校校医
ミッキーこども園園医(北仙台園、八乙女園、泉中央園、榴ヶ岡公園前園)
ぶんぶん保育園園医(二日町園、小田原園)
少林寺拳法中拳士三段
(2025年10月現在)